太りにくい“ヤセ体質”になるには?50代からでも遅くない!腸を整えよう

40~50代になると「太りやすくなった」「何をしてもやせない」と感じませんか?
大正製薬が行った「肥満に関する意識調査」の結果では、女性は、太りにくい体質になりたいと思う傾向が男性よりも強く、特に50代の女性は7割以上がやせ志向をもっているということが分かりました。同時に、多くの人は「食べ過ぎない」「基礎代謝のよい体づくり」「適度な運動」とやるべきことは分かっているものの、その実現がなかなか難しいという現実も明らかになりました(※)。
※大正製薬株式会社「肥満に関する意識調査」より
太りやすくなるのは、基礎代謝が低下していることが大きく関係しています。特に女性は、更年期になるとさらに代謝が低下し、たくさん食べたわけではないのに、太ってしまう人が増えていきます。ヤセ体質を手に入れるにはどうすればよいでしょうか?専門家に聞きました。

順天堂大学医学部卒業。順天堂大学総合診療科・女性専門外来での診療経験をもとに、便秘外来、内科、皮膚科、女性専門外来のクリニックを都内に開業。特に便秘外来は人気で、現在まで1万5000人を超える便秘に悩む患者の治療に当たっている。
太りにくい体質への近道は、“腸内環境の改善”
やせない原因は、「腸内環境の老化」かもしれません

腸内環境の老化を加速させる不摂生やストレス
不摂生やストレスによる自律神経の乱れも、腸内環境の老化と太りやすさに大きく影響します。自律神経の乱れによって腸のぜん動運動が低下すると、排便がうまくいかず、老廃物をため込むことで体重が増えていきます。さらに、栄養を適切に消化・吸収する機能が落ち、体に必要な栄養だけでなく、脂肪燃焼のために必要なビタミンやミネラルも十分に吸収できなくなって、血液の質が低下します。腸内の排出すべき老廃物を含んだドロドロの血液は、細胞に入り込めないまま全身を巡り、脂肪として蓄えられてしまうため、代謝が落ちてさらに太りやすくなってしまうのです。腸内環境の老化を防ぐには、規則正しい生活やストレス解消を心がけることも大切です。
腸内環境の老化を防ぐには、腸内細菌の「バランス」が大切
ヤセ体質をつくる “ヤセ菌”とは?
ヤセ菌の代表格は、「ビフィズス菌」

腸内には、1000種類以上の腸内細菌が存在するといわれており、その腸内細菌のバランスが、太りやすさや、やせやすさに影響するということが分かってきました。
特に最近注目されているのが、善玉菌や日和見菌が代謝物として産生する「酢酸」「酪酸」に代表される短鎖脂肪酸です。短鎖脂肪酸は直接脂肪細胞に働きかけることで、余分な脂肪の吸収を抑制し、脂肪を燃焼させる働きがあります。さらに腸のバリア機能を高めたり、全身に運ばれて臓器のエネルギー源になったりすることで、肥満を防ぐことができます。
ヤセ菌とは、この短鎖脂肪酸を産生する腸内細菌のこと。「酢酸」を生み出すヤセ菌に当たるのが、ヨーグルトなどに含まれていることでおなじみの「ビフィズス菌」です。また、腸内環境を整える「酪酸」を産生する「酪酸菌」は、食事から摂取するのは難しい菌ですが、サプリメントも発売されています。
アッカーマンシア・ムシニフィラという菌もヤセ菌として最近注目されていますが、まだ不明な点も多く、現在研究が進められている段階です。
“デブ菌”は、食習慣でブロックできる
ヤセ菌がある一方で、デブ菌と呼ばれる菌も存在します。デブ菌とは、日和見菌の中でも高脂肪、高糖質、低食物繊維などの食品を好物とし、悪玉菌を優勢にさせやすい菌のこと。食事から多くのエネルギーを取り込むため、肥満に結び付きやすい菌全般を指します。
デブ菌は、ヤセ菌と違って「この種類がデブ菌」と特定できるわけではないため、デブ菌を摂らないようにするより、デブ菌を増やさないことが大切です。
具体的な方法としては、高脂質で高カロリーな動物性脂肪食品を減らし、食物繊維を積極的に摂ること。そしてビフィズス菌を増やして腸内の善玉菌を優勢にすることで、日和見菌を善玉菌の味方につけ、腸内環境のバランスを整えることが、デブ菌の増加をブロックする近道となります。
ヤセ体質への第一歩! 徐々に表れる3つの効果とは?
効果① むくみの改善
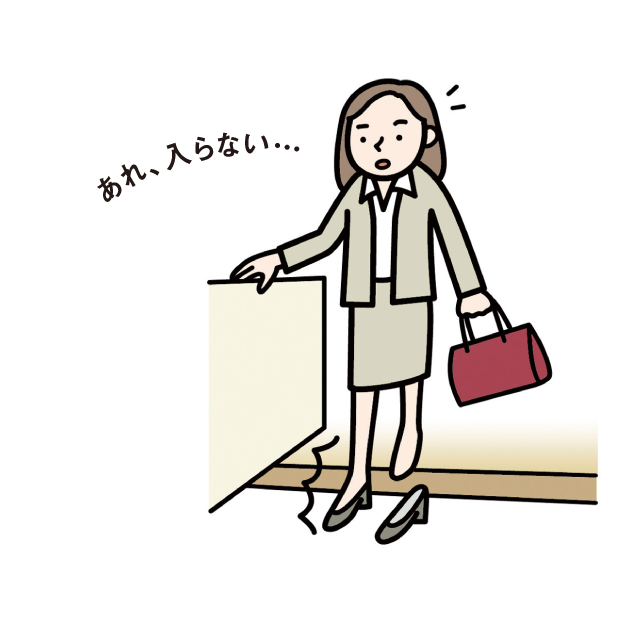
効果② 基礎代謝のアップ
効果③ 便秘解消

思い立ったが吉日! ヤセ菌を増やす生活習慣を始めよう
昔ながらの日本の食生活を心がける

質のよい睡眠をとる
適度な運動を行う
ヤセ菌を定着させ、ヤセ体質をつくる3ステップ
ステップ① ヨーグルトやサプリメントでヤセ菌を「摂取」
ステップ② 食事でヤセ菌を「育てる」
水溶性食物繊維やオリゴ糖は、プレバイオティクスと呼ばれ、胃や小腸で消化・吸収されずに大腸まで届いてヤセ菌のエサになってくれます。プレバイオティクスを積極的に摂ると善玉菌が増え、日和見菌も善玉菌の味方になって、腸内環境がさらに改善していきます。
【プレバイオティクスを手軽に摂れる食材は?】
●水溶性食物繊維
海藻類・なめこ・アボカド・長いも・おくら・とうもろこし・大豆・ごぼうなど
●オリゴ糖
バナナ・玉ねぎ・きなこ・納豆・はちみつ・にんにくなど
現代人は、咀嚼(そしゃく)回数が減っているといわれますが、食物繊維が多く含まれる物は、よくかんで消化しやすくすることが大切です。咀嚼は消化管の最初の運動。よくかむと、消化を助けて胃腸の負担を軽減する効果が期待できるだけでなく、時間がかかることで満腹感を得やすくなり、食べ過ぎを防ぐ効果もあります。ぜひ咀嚼する回数を増やすことを意識してみましょう。

ステップ③ 腸の働きをよくしてヤセ菌を「キープする」
ヤセ体質を目指すのに“遅過ぎる”ことはありません
あわせて読みたい疾患ナビはコチラ
今すぐ確認!ドクターズチェックはコチラ
もっと知りたい!動画はコチラ

「腸活」ってどうやってやるの?やり方と腸活レシピも紹介します(動画)

 製品情報サイト
製品情報サイト









