更年期のイライラや落ち込み、諦めなくて大丈夫!原因と対処法

更年期に入り、「イライラした気持ちが、抑えにくくなってきた」「ちょっとしたことで落ち込んで、泣いてしまうことがある」など、感情がコントロールしづらくなってきたと感じていませんか? 中には、周囲に迷惑をかけてしまったり、人間関係に悪い影響が出てしまったりして、悩んでいる人もいるでしょう。
厚生労働省の「更年期症状・障害に関する意識調査」では、20~50代女性の50%以上が「怒りやすく、イライラする」、50%前後が「くよくよしたり、憂うつになることがある」と回答しています(※)。女性は更年期に限らず、月経、妊娠・出産など、ホルモンバランスが変化するタイミングがあります。ホルモンバランスの変化は、身体的な症状のみならず精神的な症状も招くため、女性は、更年期に限らずイライラしたり落ち込んでしまったりしやすいと考えられます。
今あなたが悩んでいるイライラや落ち込みが、更年期によるものなのか、それとも他に理由があるのかを知るためにも、まず更年期特有の症状や原因について知っておくとよいでしょう。また、更年期による感情の起伏は、他の更年期症状を悪化させてしまうこともありますので、更年期によるイライラや落ち込みに効果的な対処法などもご紹介します。
(※)厚生労働省「更年期症状・障害に関する意識調査」
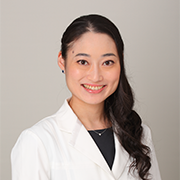
聖路加国際病院女性総合診療部、東邦大学医療センター大森病院心療内科を経て、対馬ルリ子女性ライフクリニック勤務。Addots GINZA「女性のこころとからだのオンライン相談室」開設予定。医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本心身医学会心身医療専門医、日本女性心身医学会認定医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医。心療内科、婦人科両面からのケアを行う。
更年期にイライラしたり落ち込んだりする原因
更年期の精神症状が出やすい人やその要因とは?
更年期の精神症状には、抑うつ、不安、イライラ、集中できない、気分が揺らぎやすいなどがあります。この中でも特に起こりやすく、多くの人が悩まされているのが、落ち込み、不安、不眠の3つです。これらの更年期の精神的症状が出やすい人やその要因をまとめると、次のようになります。
精神的症状が出やすい人 |
精神的症状発症の要因となるもの |
症状の悪化させるもの |
| ・PMS(月経前症候群)、PMDD(月経前不快気分障害)、周産期うつ病などに悩まされてきた人 | ・うつ病や体の疾患がある ・運動不足 ・社会的なストレス ・支えとなるパートナーの有無 |
・職場の問題や人間関係 ・家族やご近所の問題 |
更年期の精神症状なのか、もしくはそうではないのかが分からない場合は、まずは、ご自身が今どのような状況にいて、どのような症状が出ているのかを認識することが大切です。
抑うつってどんなもの? うつ病との違いとは?
更年期に生じやすい抑うつとは、一時的に憂鬱(ゆううつ)になったり落ち込んだりする状態のことで、軽度から中等度のものは更年期症状と捉えて問題なく、病気ではありません。その原因としては、更年期をもたらすエストロゲンの減少が、気持ちを落ち着かせるセロトニンなどの神経伝達物質の分泌に影響することが挙げられます。また、抑うつは身体的な更年期症状とも深く関係し、時間や場所に関係なく突然起こるホットフラッシュが精神的な負担となり、抑うつの発症につながってしまう場合もあります。
抑うつの状態が長く続いたり、生活に支障を来したりしている場合は、うつ病の可能性もあります。更年期症状を併発していることも多いうつ病ですが、抑うつとは異なり医学的に診断される精神疾患であり、治療が必要です。
更年期ならではの心理・社会的要因が大きく影響することも
更年期は、年齢的にいえばちょうど人生の折り返し地点。エストロゲンが減少し、体が変わっていくだけではなく、親の病気や介護、仕事でのキャリアアップやそれに伴う責任の増加、子どもの進学や独立など、家庭や社会において、大きな変化が続きやすい年代です。

その変化にうまく適応できないと、思うようにいかなかったりストレスがたまったりして、徐々に精神的な症状が現れてきます。さらに身体的な不調も相まって、漠然とした不安感に襲われたり、憂鬱な気分になったり、イライラや落ち込み、不安、不眠などに悩まされてしまうのです。
更年期症状があるなら、まずは婦人科に相談を
自分自身が更年期による抑うつなのかうつ病なのか、そもそも治療が必要なのかは、なかなか判断しづらいものです。「急に涙が出るようになった」などこれまでにはない変化を感じたり、症状が長く続いて生活にも支障を来していたりするなら、自己判断は避け、医療機関に相談してください。その他の更年期症状もある場合は、まずは婦人科へ。婦人科は精神科や心療内科と連携している場合も多いので、必要な対処や治療につながります。
更年期における抑うつやうつ病の治療は、薬物療法や精神療法が中心になります。代表的な薬物療法が、ホルモン補充療法(HRT)です。その名の通り、エストロゲンを補充する治療法で、経口薬(のみ薬)や経皮薬(貼り薬・塗り薬)といった様々な方法があります。抑うつに効果があるのに加え、抗うつ薬の効果も高めます。
「不安感が強い」という人は、精神科・心療内科へ
エストロゲンの減少に伴うセロトニンの働きの低下により、更年期には不安を感じたりパニックに陥ったりする人が増えるといわれています。不安症とは、漠然とした将来の脅威に対する恐れ(不安)や現実に迫る脅威に対する恐れ(恐怖)が明らかに過剰で、しかも長期間持続し、生活に支障を来している状態のこと。不安感をコントロールできなかったり、漠然としたことにも強い不安を感じたりするなら、女性ホルモンの変化以外に要因がある可能性も。そのような場合は、婦人科ではなく精神科や心療内科を受診しましょう。
病気や他の原因がある可能性も
イライラや落ち込みといった精神的な症状には、次のような他の原因も考えられます。
●精神疾患
うつ病や躁うつ病の他、不安症、適応障害などで感情の起伏が激しくなることがあります。症状は多岐にわたります。女性は女性ホルモンのバランスの変化に精神的な要因が加わる場合も多く、その治療には、婦人科と精神科や心療内科との連携が必要になります。
●甲状腺機能障害
甲状腺ホルモンが過剰につくられるバセドウ病や、逆に甲状腺ホルモンが不足する橋本病など。全身の代謝を調整する甲状腺ホルモンの過不足で自律神経のバランスが崩れ、イライラや落ち込みが生じる場合があります。特に橋本病は更年期の女性に多い病気です。
●鉄欠乏性貧血
月経やダイエット目的の偏った食生活などにより、特に女性に多く見られます。セロトニンの生成には鉄が必要なため、鉄が不足すると心の不安定さを招くことがあります。また、貧血になると体内の酸素や栄養の巡りが低下して疲れやすくなり、精神的な症状を含めた更年期症状を悪化させる場合もあります。
●薬の副作用
一部のステロイド剤や高血圧薬、抗てんかん薬、抗うつ薬や抗不安薬、抗がん剤、免疫抑制剤、ピルなどの副作用で起こることがあります。
●アルコールやカフェイン、たばこの影響

・アルコール
飲酒をすると、感情が抑制しにくくなったり、アルコールが体から抜けていく過程でイライラや落ち込みが生じたりします。大量の飲酒を続けていると、脳が萎縮して怒りっぽくなることもあります。
・カフェイン
交感神経を刺激するため、精神が不安定になり感情の起伏が激しくなる場合があります。
・たばこ
喫煙によって体内に取り込まれるニコチンや一酸化炭素などは、エストロゲンの働きを低下させるため、精神的な症状を含む更年期症状に影響します。
更年期のイライラや落ち込みの対処法
対処法① セロトニンの分泌をよくする生活習慣
更年期のイライラや落ち込みには、生活習慣を見直して、心を落ち着かせるセロトニンの分泌を促してみましょう。
●朝日を浴びて朝食を摂る
起床したらまず朝日を浴び、朝食を摂ることでセロトニンの分泌が促されます。セロトニンは睡眠ホルモンであるメラトニンの材料にもなるため、更年期に悩まされやすい不眠の改善や、睡眠の質の向上にもつながります。
更年期の睡眠については、コラム「眠れない、眠りが浅い……それって更年期のせい? まずは自分の睡眠を知ろう」もご覧ください。
●有酸素運動をする
セロトニンは、一定のリズムで行うウォーキングや自転車こぎ、踏み台昇降といった有酸素運動でも分泌されます。有酸素運動によるセロトニンの分泌効果はとても高いので、息が上がる・心臓がドキドキするくらいの運動を、1回20分、週に2、3回以上継続するのがおすすめです。日々の忙しさに追われて運動をする時間が取れない時におすすめなのが、ガム。ガムを噛むこともセロトニンの分泌を促すリズム運動になります。
●セロトニンの原料となるトリプトファンを摂る
セロトニンの原料となるトリプトファンを含む、豆腐・納豆・みそなどの大豆製品、牛乳やヨーグルトなどの乳製品、米などの穀類、ナッツ、卵、バナナなどを積極的に摂取しましょう。これらを朝食で摂ると、女性ホルモンの減少によって乱れやすくなる体内時計も整えられます。セロトニンのほとんどは腸で生成されるので、腸内環境を整え、腸の働きを高めるとより効果的です。
腸内環境の整え方については、コラム「腸内環境の整え方を知ろう。ドアノブからも腸内細菌はうつるって本当?」もご覧ください。
●鉄やビタミンC、ビタミンB群、マグネシウムを意識的に摂取する
セロトニンの分泌を促すためには、鉄欠乏性貧血の原因となる鉄、抗ストレスホルモンの生成に消費されるビタミンC、神経伝達物質の生成に不可欠なビタミンB群、精神状態を安定させるマグネシウムの4つの栄養素を意識的に摂りましょう。これらの栄養素が多く含まれる食材をご紹介します。
鉄 |
赤身の肉やレバー、ほうれん草など |
ビタミンB群 |
玄米や雑穀などの未精製の穀物、肉、魚、豆など |
ビタミンC |
オレンジ、いちご、キウイフルーツ、ピーマンなど |
マグネシウム |
マグロ、サーモン、牛レバー、バナナ、アーモンド、トマト、アボカドなど |
このような食材を日々の食事で摂るのが難しい場合は、サプリメントなどで補ってもよいでしょう。以前は、「イライラにはカルシウム」といわれていましたが、血液中のカルシウム濃度は安定するようになっているため、俗説であることが分かっています。
対処法② 「マインドフルネス」と「アンガーマネジメント」で素早くコントロール
イライラや落ち込みをコントロールしたい時、感情の乱れを抑えたい時に有効な方法です。
マインドフルネスとは、仏教で悟りを開くための瞑想法を体系化したもので、「今、この瞬間」の自分の感覚や思考に意識を向けることを指します。自分の思考や感情を客観的に観察することで、自分のよいところも悪いところも受け入れることができるようになり、それによってストレスの軽減や集中力の向上など様々な効果が期待できるとされています。
一方アンガーマネジメントとは、怒りやイライラを感じた時に、その感情をコントロールして冷静な判断を促すための有効な手法です。
この2つの考え方や手法を取り入れることでイライラや落ち込みに振り回されにくくなり、心穏やかに過ごせるようになります。
【普段から取り入れられる! マインドフルネスの具体的な方法】
●呼吸(呼吸瞑想)
呼吸は、特に道具も必要ないのでいつでもできます。就寝前や起床してカーテンを開けた時、仕事の休憩時間など、取り入れやすいタイミングや気がついた時に行って習慣化してみましょう。
①静かな場所で、背筋を伸ばして座る
②目を閉じて、自分の呼吸に意識を集中する
③深呼吸を行い、呼吸のリズムに気持ちを合わせる
④雑念が浮かんだら、再び呼吸に意識を戻す
⑤一定の時間が経ったら、徐々に意識を日常に戻す
●食事(食事瞑想)
次のことに留意しながら食事とじっくりと向き合うと、ストレスから解放されるのと同時に、過食を防ぐ効果も期待できます。

・食事に集中する: 食事中はテレビやスマートフォンを見ずに、食事そのものに意識を向ける
・五感を使う: 食べ物の色、香り、味、食感を意識的に感じ取る
・ゆっくりと味わって食べる:一口ずつよく噛んで、食べ物の味や食感を十分に楽しむ
・空腹と満腹のサインに注意を払う: 体からのシグナルに耳を傾け、適量を心がける
●ウォーキング(歩行瞑想)
次のような方法で歩くと、5~10分でも効果がありますが、気持ちがよければ無理のない範囲で継続してもいいでしょう。「瞑想するために歩かなきゃ」と無理に取り入れなくても、駅からオフィスまで、買い物に行くお店まで、ペットとのお散歩など、意外と普段から歩く機会はあるものです。
①リラックスして立ち、歩く前に何度か深呼吸をする
②足の裏に意識を向けて地面を感じる
③自然のままに数回呼吸し、ゆっくり歩き始める
④足の裏の感覚を意識しながら歩く
⑤脚、背中、腕など、足以外の部分がどう動いているかを感じる
【怒りやイライラが起きた時に実践してみよう! アンガーマネジメントの具体的な方法】
●6秒数える

怒りを感じた瞬間に、冷静になる時間をつくると感情の爆発を防ぎやすくなります。深呼吸を2~3回ゆっくり行う、頭の中で数字を1から6まで数える、コップ1杯の水を飲むなど、一呼吸置けるルールを設けてみましょう。怒りのピークは約6秒といわれており、その間に反射的な行動を取らないことが重要です。
●怒りの数値化
自分の怒りを10段階で評価する時間を設けます。「今の自分の怒りは3くらいだ」など、一度自分で怒りの自己採点をすることで、感情に流されることを防ぎます。
●その場を離れる
怒りが収まらない時は、その場を離れてみましょう。冷静になる時間をもつことで、より理性的に対処できるようになります。
●自己観察
自分がどのような状況で怒りを感じるのかを把握するために、メモ程度でいいので感情を記録して、自分のパターンを理解するのも効果的です。
●トリガー分析
自分が怒りを感じる特定のできごとや人を特定し、その原因を探ります。
完璧じゃなくて大丈夫! 日々の暮らしは「60点」を目指しましょう

更年期の不眠、イライラ、落ち込み、不安感、ホットフラッシュなどといった症状は、とてもつらく悩ましいものですが、生活習慣や気のもち様を変えることで、症状を軽減させることは可能です。もし今、生活リズムに乱れがあるなら、その生活を見直して、質が高く十分な睡眠をとり、適度な運動を習慣化し、栄養バランスのよい食事を規則正しく摂るとよいでしょう。しかし、そんな聖人君子のような生活は、なかなかできるものではありません。むしろ、「できなくて当たり前」なのです。
更年期症状は、物事を楽観的に受け止めるタイプの人よりも、完璧主義の人や自己犠牲をいとわない人に出やすいとされています。だからこそ、何事においても「完璧」を目指さないという考え方が大切です。「できないこと」があったっていいのです。日々の生活においては、60点くらいを目指すつもりで過ごしてみてください。そうすれば、プレッシャーやストレスから解放されて、心が軽くなるでしょう。
我慢をせず、周囲の力も借りましょう
もし気になることや、不調を感じたら医療機関を頼ればいいですし、食事で十分な栄養が摂れない場合はサプリメントで補ってもいいでしょう。悩みやつらさを抱え込んで、自分で全部やろうとせずに、周囲のサポートをうまく利用することが大切です。生活習慣や運動習慣、食事の改善、マインドフルネスやアンガーマネジメントなど、更年期症状への対策はいろいろありますが、一気にやろうとしなくても大丈夫です。焦らずに、自分が取り入れやすいことから、少しずつ始めてみましょう。
更年期は誰にでもやってくるものです。そこからくるイライラや落ち込みなどの心の不調は、自分の甘えやわがままによるものではありません。だから自分を責めず、1人で抱え込まずに周囲の力も借りながら対処して、少しでも楽に、健やかに、更年期を過ごしましょう。
 製品情報サイト
製品情報サイト











